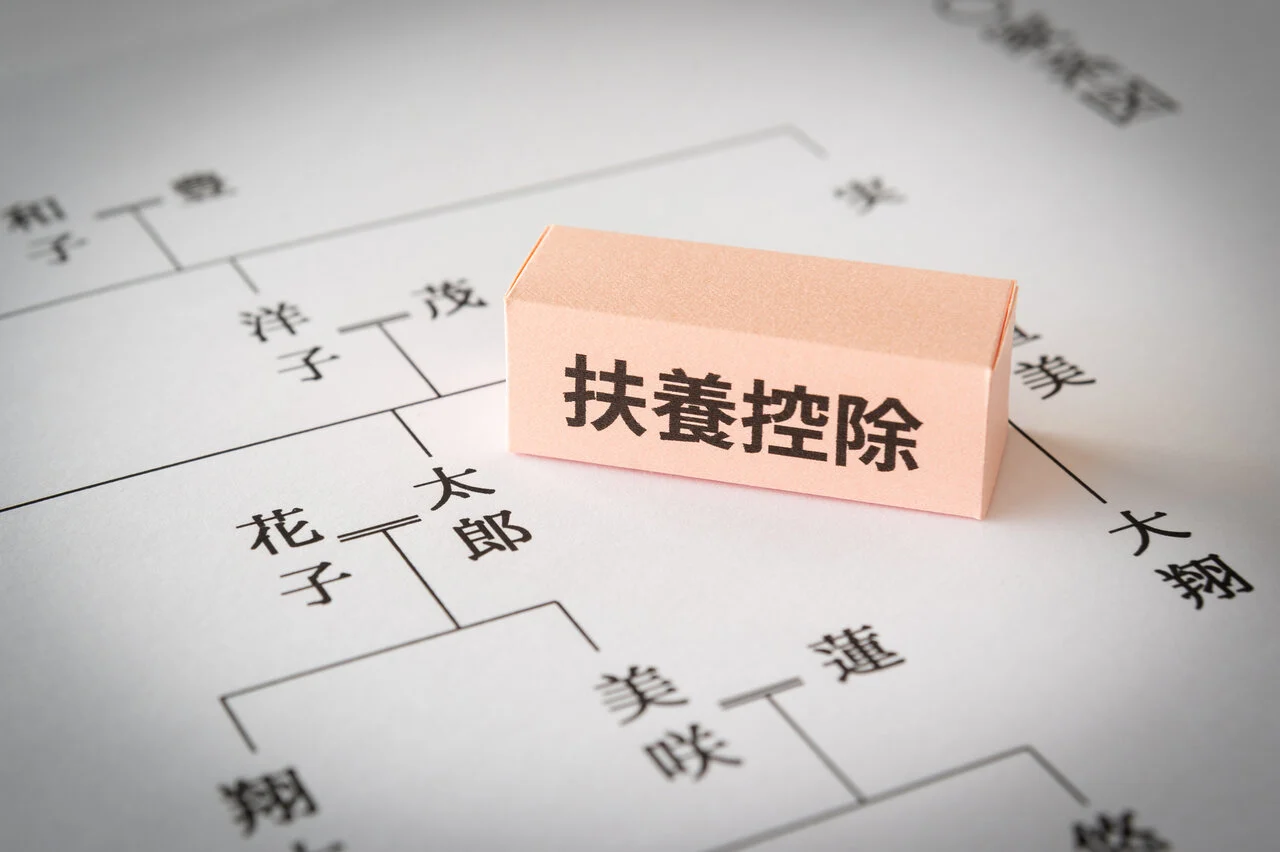会社員がiDeCoへの加入を検討する際、節税効果が高いといったメリットがあることは知っている一方で、デメリットまで理解できていない人も多いのではないでしょうか。
安易にiDeCoに加入してしまうと、「思ったより節税効果が見込めない」「掛金によって生活費が圧迫されている」などの状況に陥ってしまう恐れがあります。
今回の記事ではそうした事態にならないよう、iDeCoの概要やが会社員がiDeCoに加入するメリット・デメリットについてまとめてみました。

iDeCoとは?特徴を初心者向けにわかりやすく解説 | @nextマガジン | @next(アットネクスト)
iDeCoの仕組みとは?
個人型確定拠出年金であるiDeCoは、自分が拠出した掛金を自身で運用し、老後の資産形成をする私的年金制度のことです。
毎月一定の金額を積み立てながら運用し、60歳から75歳までの間に老齢給付金として受け取る仕組みとなっているほか、原則として60歳まで資産を引き出せないといった特徴があります。
iDeCoで運用できる商品には、定期預金や保険など「元本確保型」と呼ばれる安全性が高いものと、投資信託など価格変動のある「価格変動型」の2種類があります。
それぞれの特徴を考慮したうえで、自分に合ったものを選ぶことが大切です。
iDeCoには3つの節税効果がある
iDeCoには主に、以下3つの節税効果があります。
・掛金が全額所得控除になる
・利息や運用益が非課税の対象になる
・受け取る際に税制優遇がある
iDeCoで支払った掛金は全額が所得控除の対象となり、確定申告や年末調整で申告すれば当年分の所得税と翌年分の住民税の減額が可能です。
また、通常であれば投資の運用益に対して20.315%が課税される一方、iDeCoで得た運用益や利息には税金がかかりません。
利益をそのまま受け取れるのはiDeCoの大きな利点だといえるでしょう。
その他、受け取る際にも税制優遇があり、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の中から好きな受取方式を選択できます。
「一時金」を選んだ場合は退職所得控除、「年金」の場合は公的年金等控除が適用されます。
運用リスクが伴う点に注意が必要
iDeCoは私的年金制度であるものの、投資のひとつです。
そのため、運用には一定のリスクが伴う点に気を付けなくてはなりません。
先にも述べたように、iDeCoで運用できる商品には元本確保型と価格変動型の2種類があり、その中でも価格変動型は大きなリターンが見込めるものの、運用成果次第では損失が生じる恐れがあります。
自身のリスク許容度を踏まえたうえで運用商品を選ぶことはもちろん、分散投資を心がけるようにしましょう。
iDeCoと企業型DCはどう違うの?
iDeCoを検討している人の中には、企業DCと何が違うのかいまいちよくわからない人も多いのではないでしょうか。
iDeCoが自助努力の制度であるのに対し、企業DCは福利厚生制度の1つです。
そのため、iDeCoでは手数料を加入者自身が負担しますが、企業型DCでは会社が負担してくれます。
運用商品の選定も企業型DCでは会社が行ってくれるため、投資知識があまりない方にとってはiDeCoよりも企業型DCのほうが利用しやすいといえるでしょう。
また、iDeCoと企業DCの違いについて下表にまとめてみました。
【iDeCoと企業型DCとの違い】
| iDeCo | 企業型DC | |
|---|---|---|
| 加入対象者 | 20~60歳 | 企業型DCを取り扱っている会社に勤めている会社員 |
| 運用する人 | 加入者 | 会社 |
| 拠出限度額(会社員) | 12,000~23,000円 | 27,500円~55,000円 |
| 積立期間 | 65歳まで | 65歳まで |
| 掛金に対する税制優遇 | 全額所得控除 | マッチング拠出の場合、加入者掛金は全額所得控除 |
| 運用にかかる手数料 | 加入者 | 会社 |
企業型DCとiDeCoの併用は基本的に可能ですが、企業型DCのマッチング拠出を利用している場合は加入することはできない点に注意しましょう。
会社員がiDeCoに加入するメリット

会社員がiDeCoに加入するメリットとして、主に以下の2つが挙げられます。
転職しても資産を移転できる
iDeCoで積み立てた掛金は転職先の企業へ移転可能です。
一度精算する必要なく、途切れずに運用が続けられるため、安定して資産形成を行えるでしょう。
ただし、資産を移転できるのは、転職先の企業がiDeCoの運用を認めている場合に限られる点に注意が必要です。
企業年金と別に年金が確保できる
iDeCoに加入することで企業年金と別に年金が確保できるのも大きなメリットです。
会社員には退職金制度(退職一時金や企業年金)があるため、退職をすることに不安を感じる人も多いかもしれません。
その点、iDeCoに加入しておけば、年金を確保できるため、万が一退職することになっても安心といえるでしょう。
会社員がiDeCoに加入するデメリット
会社員がiDeCoに加入する際、メリットがある一方で以下のようなデメリットもあります。
転職する際に掛金の上限額が変動する恐れがある
転職先の企業年金の有無によって、掛金の上限額が変動する点に注意が必要です。
それぞれの拠出額の上限は以下のようになります。
| 拠出額の上限 | |
|---|---|
| 企業型DCがない企業の会社員 | 月額23,000円 |
| 企業型DCに加入している企業の会社員 | 月額20,000円 |
| 企業型DCと企業型DB(確定給付年金)に加入している企業の会社員 | 月額12,000円 |
| 企業型DB(確定給付年金)に加入している企業の会社員 | 月額12,000円 |
※2024年12月以降は、月額55,000円から企業形DCの事業主掛金と企業型DBなどの他制度掛金額を差し引いた金額(上限月額20,000円)が掛金額の上限となる
転職先が企業年金を取り入れている場合、掛金の上限額が減少してしまうケースも考えられます。
「将来の年金として物足りない」と感じることのないよう、転職先の取扱いや規約について、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

iDeCoの掛金は毎月いくらに設定すべき?掛金の平均や上限、拠出額の決め方を解説 | @nextマガジン | @next(アットネクスト)
資産を移転する場合は運用商品を売却しなければならない
転職に伴い資産を企業型DCへ移転する場合、いったん運用商品を売却する必要があります。
転職先の規定に合わせて買い直さなくてはならない点に注意しましょう。
受け取る際に税制優遇を受け取れないケースがある
勤めている企業から退職金や年金を受給する場合、退職所得控除や公的年金等控除の限度額に達してしまい、iDeCoを老齢給付金として受け取る際に税制優遇を満額使用できないケースがあります。
先にも述べたように、老齢給付金として受け取る場合、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3つから選ぶことが可能です。
一時金で受け取る場合、「退職所得」として退職所得控除の対象となり、以下の控除額が適用されます。
| 掛金の支払い年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×掛金の支払年数(80万円未満は80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(掛金の支払年数-20年) |
※掛金の支払年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げる
一方、年金で受け取る場合は「雑所得」の扱いとなり、公的年金等控除の対象です。
以下の控除額が適用されます。
| 年金以外の所得額 | 年齢 | 非課税額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 65歳未満 | 60万円 |
| 65歳以上 | 110万円 | |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 65歳未満 | 50万円 |
| 65歳以上 | 100万円 | |
| 2,000万円超 | 65未満 | 40万円 |
| 65歳以上 | 90万円 |
ここで注意したいのが、この金額は厚生年金や国民年金も合わせた金額となることです。
非課税額よりも受け取る額が多い場合、所得税や住民税などが発生してしまう恐れがあります。
このように、受け取り方によって税負担が生じる恐れがあるため、自分にあった最適な方法を確認しておくようにしましょう。
iDeCoが向いている会社員とは?
会社員がiDeCoに加入する際のメリット・デメリットを理解したうえで、向いている人は以下のとおりです。
・余裕資金がある人
・勤務先に企業DCの取扱いがない人
・企業DCに上乗せして資金形成をしたい人
iDeCoをはじめとする投資は、余裕資金で行うことが大前提です。
そのため、たとえ老後の資金不足に備えるためとはいえ、余裕資金がない状況でiDeCoに加入してしまうと、生活に支障を及ぼす恐れがあります。
今後のライフプランを考慮したうえで、iDeCoを加入するか否かを判断するようにしましょう。
また、勤務先に企業DCの取扱いがない人や、企業DCに上乗せして資産形成を行いたい人にもiDeCoは向いています。
運用を始める際は、リスクを理解したうえで必要に応じて加入することがおすすめです。
iDeCoできちんと老後形成をしよう

今回の記事では、会社員がiDeCoに加入するメリット・デメリットについてお伝えしました。
iDeCoは将来に備えて資金を確保したい人におすすめである一方、状況によってはメリットである税制優遇が受けれないケースも見受けられます。
また、掛金の確保による生活への圧迫や元本割れなどのデメリットについても理解しておかなければなりません。
そのため、iDeCoに加入する前にはリスクについて把握したうえで、自身の置かれている状況でメリットが十分に得られるかどうかを確認することが大切です。